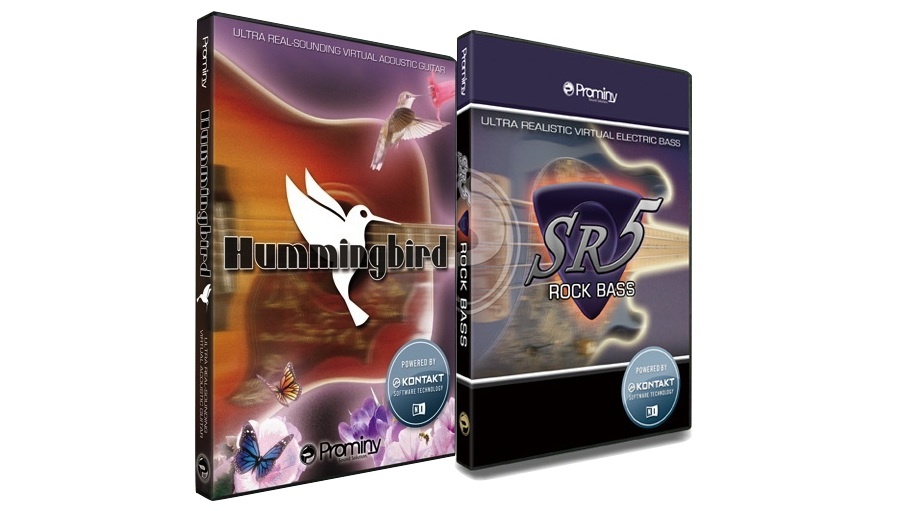UVI Thorusが2月19日まで税込¥5,940に!
KORG prologue 予約受付中!独自の進化を遂げた、最大16ボイス フルプログラマブルのフラッグシップアナログシンセ
NAMM 2018で話題となったKORGのフラッグシップアナログシンセ prologueのご予約を受付中です!
prologueは鍵盤数とボイス数が違う2製品のラインナップ。特にアナログとデジタルのハイブリッドなオシレーター『マルチエンジン』はライバル機との違いを明確にアピールしています。さらに最大500も保存したプログラムをソートで簡単に呼び出せたり、コンプレッサー部に搭載されたアナログメーターやmonologueで人目を引いた波形ディスプレイでユーザーの所有欲も満たします。
prologueはサウンド、ユーザビリティ、外観まであらゆる面でフラッグシップにふさわしい、KORGの自信作です。
- prologue-16 … 61鍵(16ボイス)
- prologue-8 … 49鍵(8ボイス)
prologue
特徴
- 16 / 8ボイスを誇るアナログ・シンセサイザー回路
- ノイズ、VPM、ユーザーの3タイプを搭載した新開発のマルチ・エンジン
- ハイクオリティなデジタル・エフェクト
- ユーザー・カスタマイズ可能なオープン環境
- 新開発のアナログ・エフェクト L.F. COMP.(prologue-16のみ)
- バイ・ティンバーに対応
- ボイスを柔軟に組み換えられるボイス・モード
- 多彩なタイプとレンジ設定を備えたアルペジエーター
- 500のプログラムに素早くアクセスできるプログラム・ソート
- 日本製の上質なナチュラル・タッチ鍵盤
- 波形を視覚的に表示するオシロスコープ機能
- アルミとウッドによるタフでスタイリッシュなボディ
- シンクすることで他のグルーヴ・マシンとセッション可能
- 16ボイス + 61鍵モデル、8ボイス + 49鍵モデルをラインナップ
アナログ+デジタルハイブリッド マルチエンジン オシレーター
4ボイス・ポリフォニックのminilogue、モノフォニックのmonologueで定評あるアナログシンセ回路に加えて、新開発の『マルチエンジン』を搭載。2つのアナログオシレーター、そして3つめのオシレーターにデジタルのサウンドが加わっています。
マルチエンジンはFXやパーカッションに有用な『ノイズ・ジェネレーター』、FM変調の『VPM(Variable Phase Modulation)』、そしてユーザーが自分でオシレータープログラムをダウンロードして使える『ユーザー・オシレーター』の3種。アナ/デジ ハイブリッドで自由度の高いサウンドメイクが可能です。他社のハイエンドアナログポリシンセとの差別化を明確にしてきた印象です。
デジタルFX
オリジナルのデジタルFXを搭載。これ1台で変調や空間演出が容易にできます。そしてアナログコンプとブースターはprologu-16に限りVUメーターでかかり具合確認できるという、KORGらしい遊び心満点な仕様。
演奏者のためのバイティンバー
さらにプレイヤーに嬉しいのは『バイ・ティンバー』に対応していること。一般的なレイヤー、スプリットはもちろん、メイン・ティンバーとサブ・ティンバーがなめらかに切り替わるクロスフェードモードも搭載しています。
まるでソフトシンセ!プログラム・ソート
prologueはプログラムを最大500保存可能。そしてそのプログラムの中から任意のサウンドをさっと探し出せる8種類のプログラム・ソートを装備。これらを使うことでほしいサウンドにすぐたどり着けます。まるでソフトシンセのようですね。
8つのプログラム・ソート
- PROG NUM … プログラム・ナンバー順にソート
- CATEGORY … プログラムのカテゴリー順にソート
- ALPHABETICAL … プログラムのアルファベット順にソート
- LIKE … “Like”が設定されたプログラムをソート
- FREQUENT … プログラムの使用回数順にソート
- ENVELOPE … エンベロープの形によってソート
- RANDOM … ランダムにソート
- LIVE SET … ライブ・セットに登録したプログラムをソート
iZotope Valentine’s Day “Love your Vocals”キャンペーン!理想のボーカルを追求する専用プラグインとRX6が期間限定プライスオフ!
iZotopeからのヴァレンタインデープレゼント!(本国は日本より遅れてヴァレンタインデーです)
ボーカル専用プラグインスイーツ『Nectar2 Production Suite』とボーカルを再形成するクリエイティブな『VocalSynth』を期間限定でディスカウントいたします。作曲からミックスまで、ボーカルエディットを追求できるプラグインをこのチャンスに!
2018年2月28日までの期間限定!

VocalSynth
VocalSynthは、電子的なボーカルの質感や、ロボットボイス、コンピュータ処理されたハーモニー、ボコーダーやトークボックスエフェクト、分厚いオクターブまたはダブルボイスを作成するためにあなたの声を形成し操作することを可能にするクリエイティブなマルチエフェクト・プラグインです。
●四つの先進のボーカルエンジン:
VocalSynthのウェーブテーブルシンセサイザーまたはサイドチェインされたインストルメントは声と一緒に使用することで-シンセサイズされたコンピューターボイスや、有機的なハーモニー、グリッチーなデジタル・スピーチ、および歌うシンセサイザー・サウンドのための基盤の音として使用できます。
●ボーカルのための洗練されたエフェクト:
エッジの効いた、もしくは洒落たディストーションや、フィルタ、スピーカー・コンボリューション・モデリングや、狂気のビート・リピート、およびワイドなステレオ・ディレイを追加して更に声のキャラクターを形成することができます。
●ピッチ補正:
リアルタイムピッチ補正を使用して音程の外れたボーカルを簡単に正しく修正します。このアルゴリズムはピッチと一緒にフォルマントを変化させるのではなく、より自然なサウンドを得るためにオリジナルのフォルマントとボーカルの音色を維持できます。
●自動またはMIDIボイスの生成:
MIDI入力を必要とせずに自動モードで複数のハーモニー、オクターブ、またはユニゾンを追加することができます。ボイス数と音程の間隔を選択するだけで、後はVocalSynthが自動で処理してくれます。もしくは、MIDIコントローラーを接続することで、VocalSynthから必要なハーモニーボイシングを正確に出力することができます。
●プリセット:
お気に入りの曲から有名なボーカル・プロダクション・テクニックの素晴らしいサウンドにすぐにアクセスできます。
Nectar2 Production Suite
Nectar 2は唯一無二のボーカルに特化した完全なツールセットです。プレート・リバーブ、ハーモニック・サチュレーション、そして豊富で創造性豊かなエフェクトがボーカルトラックに息吹を吹き込みます。また、長々と編集作業に時間を浪費することなく、音程を合わせ、不必要なブレス音を取り除くことが可能です。
- 新しいハーモナイザーがボーカルトラックにハーモニクスを追加することにより、みずみずしいコーラスや、旋律の美しいバックグラウンド・ボーカルを作り出します。インテリジェントな自動設定や、MIDIコントローラーの使用による手動での作業が可能です。
- EMT 140をモデルにしたプレート・リバーブ・モジュールがボーカルに古式ゆかしい空間やキャラクターを付与し、内蔵された独特のサチュレーション操作がプレート用プリアンプ特有の色彩を奏でます。
- 新しいピッチエディターやブレスコントロール・プラグインにより、最高のボーカルテイクが簡単に用意できます。
- 新しいFXモジュールに含まれる7つの新しいクリエイティブなエフェクトが、ボーカルサウンドの音像を豊かに拡張します。
- 最新式のオーバービュー・パネルがシンプルな調節を簡単にし、追加されたメーターが視認性を高めるほか、150以上の新たなプリセットがクラシックからモダンな音楽まで幅広いジャンルを網羅します。
Vocal Bundle
これが一番お得!「VocalSynth」と「Nectar2 Production Suite」とのバンドルです。
RX6へのアップグレードも安い!
グラミー賞を受賞した Bladerunner 2049やThe Shape of Waterなどに使われているRX6へのアップグレードも期間限定で安い!
期間:2018年2月28日まで
PREMIER SOUND FACTORYの注目音源「箏姫かぐや」が登場!ハイクオリティの音色を確認
皆さん2018年も始まりましたが、楽曲制作捗っておりますか?PD安田はいい加減、Key Gから脱却したいと思っております。今年はB♭とか、吹奏楽でもできそうな曲に挑戦していきたいと思います。
さて、この度紹介させて頂くのは「Drum Tree」でも話題を呼んだPREMIER SOUND FACTORYから新しい注目の音源「箏姫かぐや」がいよいよ発売となるとのことで!どんな感触なのか、使い勝手も含めて早速デモ曲を作ってみました!ということで、まずは確認してみてください。
1)音質には影響させない!トコトコんこだわったサウンドクオリティ
 まず初めに箏姫かぐやには13弦、17弦タイプ&フレーズ集が用意されています。そこで13弦のベーシックに立ち上げて、弾き始めると…一番のポイントは何と言っても弦の響きを増幅させる甲の深み。これを音源にするのは収録サンプルもそうですが、ICHIRO氏の録りを含めた音へのこだわりがよくわかります。太さだけではなく、豊かな倍音と響きのニュアンスは日本楽曲に留まらず、ぜひどんなジャンルでもガンガン活用して頂きたいです。
まず初めに箏姫かぐやには13弦、17弦タイプ&フレーズ集が用意されています。そこで13弦のベーシックに立ち上げて、弾き始めると…一番のポイントは何と言っても弦の響きを増幅させる甲の深み。これを音源にするのは収録サンプルもそうですが、ICHIRO氏の録りを含めた音へのこだわりがよくわかります。太さだけではなく、豊かな倍音と響きのニュアンスは日本楽曲に留まらず、ぜひどんなジャンルでもガンガン活用して頂きたいです。
そしてDrum Treeと同様に、音源の構成はシンプルで、立ち上げたすぐには双方のボタン(キースイッチにて切り替え可能)があり、マイキングの「Stereo」と「Center」のレベル調整。
さらにさらにReverbの項目ですが、デフォルトではコンボリューション・リバーブが選ばれていますが、何と言ってもすごいのが…「Lunar Kaguya」というロングリバーブが用意されています。
ちなみに、後ろでアルペジオのように演奏しているサウンドには「Lunar Kaguya」の1番をガンガンに使用してみました。全然邪魔しないリバーブなので、びっくりです。
本当はバンドっぽくピアノとかも混ぜてみたかったのですが、これで完結したというのと、琴のクオリティだけでも十分な濃厚さがあるので、ベースとドラムの3ピースです。そんなインストバンドあったらいいですね。
2)直感的でアイデアも浮かぶ要素満載の機能!
 前述で述べたのは表の奏法などパラメータ関連がありましたが、違うタブの「Scale」に行くと、ここではお琴の高域部分を拡張できる機能が搭載。普通は13弦なので、音階は決まってきますが、欲を出して欲しいトーンを決めることも可能です。そこでさらにですが、スケールプリセットも36個用意されており、しかも琴のイラストから1部だけトーンを変えることができます。(ユーザープリセットとして保存も可能)
前述で述べたのは表の奏法などパラメータ関連がありましたが、違うタブの「Scale」に行くと、ここではお琴の高域部分を拡張できる機能が搭載。普通は13弦なので、音階は決まってきますが、欲を出して欲しいトーンを決めることも可能です。そこでさらにですが、スケールプリセットも36個用意されており、しかも琴のイラストから1部だけトーンを変えることができます。(ユーザープリセットとして保存も可能)
Key Gの曲はいい加減…って言いましたが、結局デモ曲で選んだプリセットは3つの構成で「33,Minyo (Major)」「36,Tone Kaze」「28,Sofuren1 (Major)」でしかも一部F#を加えている(主線の琴)とルールから逸脱したデモ結果となっています。あえてクロマチックは使用しませんでしたが、やはり音が続いて行くときの共鳴感などはプリセットのスケールを選ぶと全体の響き感に影響してきます。
ただ、いろいろプリセットを選ぶ中で、琴をメインに作ってみた感想として、縛りのある音階の中から作り上げるのはなかなかやりがいがあるのと、作曲においてもいい勉強になります。日本の伝統的な曲を参考にしつつ、ベースの音の動きを踏まえて、その上で琴がどう乗るか。是非、琴を主体とした楽曲作りをやってみて欲しいですね。
話が脱線しましたが、スケールのプリセットが選択できるに加えて、琴姫かぐやの素晴らしいのはトレモロ(F#,G#,A#)がトップノートと同音が自動的に配置されます。奏法の項目にもトレモロはありますが、通常の奏法からでも簡単にトレモロを入れて行く且つ、別の音を加えて行くことができます。しかし演奏者ならではの弾き方やテクニックがあるのかと思いますので、もっと研究は必要ですね(押し離しとかの入れ方など、おしゃれな聴かせ方はたくさんあるはずです)
3)MIDI打ち込みの試行錯誤
さて奏法がいくつか用意されておりますが、これらはキースイッチで切り替えが可能です。MIDIの打ち込み方はきっと人それぞれかと思いますが、奏法を変えたい手前に打ち込めばもちろん瞬時に切り替わります。特にですが、押し離し,すくい爪,後押しなどなど、結構部分部分に使用したい奏法が時と場合によって必要になってきます。触ってみて思いましたが「1本だけでは無理!」なので、KONTAKTでMIDIチャンネルを分けて複数立ち上げて使用するとベストかと思います。ちなみに重さに関しては、比較的軽い動作なのではないかと思います。
そして、通常の弾きでメインになるのは爪での演奏ですが、ベロシティによってピッキングのニュアンスが変わってきますので、しっかり音の強弱も加えていきたいところです。今回のデモでは100を基本として打ち込んでいますが、強調したい部分は127に、完全に弱い部分は57ぐらいになっています。弱くしても強弱はありつつ、音が見えてくるのはやはりいい音で収録されているからが理由ではないかと思います。
とここまで、実際に触ってみて作ってみて感じた事を書いてきました。やはり琴に関してはこの音源を機に楽器の知識と、スケールから編成のパターンなどいろいろ知っておく、調べておく必要があるかと思います。なので、皆さんも琴姫かぐやを導入したら、是非調律も合わせて、与えられた枠の中で作ってみてください。
さていかがだったでしょうか?PREMIER SOUND FACTORY社の音源はクオリティはもちろんだが、何よりも操作性がシンプルで、しっかり使う人のことを考えられている設計になっているのが今回も改めてわかりました。まだPREMIER SOUND FACTORY社はこれからも新しい音源を開発して行くとのことなので、是非次回作も期待をしたいところで、またもともと扱っていた音源達も是非当店でも取り扱えるようにしていただきたいと思います!皆さんもぜひこの機会に挑戦とともに、導入をご検討ください!
KORG 2018 新製品内覧会レポート!

2018年2月9日に都内某所にてKORG 2018 新製品内覧会が開催されました。その模様をレポートします。
prologue
まずはNAMM 2018でも紹介されていたアナログシンセサイザーprologueです。創立50周年を迎え、今年最初の大型製品。
minilogue、monologueと来て登場した第3弾、待望のフラッグシップモデルの登場です!
製品の概要をKORG開発担当の山田氏に解説していただきました。
沢山アナログシンセ作ってきた音作りのノウハウを活かしながら、細かい部品選定や回路レベルで音をよくすることに集中して開発したということです。minilogue、monologueでは入れられなかった機能もprologueには盛り込んだということです。これは期待が高まりますね。
prologueの大きな特徴はアナログオシレーター2基に新開発のデジタルオシレーター『MULTI ENGINE』が搭載されたことです。このMULTI ENGINEにノイズ・ジェネレーター、FM変調のVPM(Variable Phase Modulation)、そしてユーザー・オシレーター(WAVE TABLE)の3種類があります。ユーザーが自作のオシレーター・プログラムをロードできるのは驚きですね!どんなデジタル・オシレーターを組み合わせればアナログ・シンセに効果的な作用をもたらすのか、色々と試してみたくなります。
いよいよお待ちかね、サウンドを聞いてみましょう。前述の山田氏による実演を交えたprologueの解説がありました!
- 0′00″〜 prologue概要
- 0′59″〜 アナログコンプの効果について
- 1′57″〜 デジタルオシレーターの紹介
- 3′31″〜 アナログとデジタルオシレーターを組み合わせた音色
- 4′32″〜 エフェクトについて
- 6′52″〜 アルペジエイターを組み合わせたデモ演奏
デジタルオシレーターのMULTI ENGINEサウンドが実に変化に富んでいましたね!エフェクトもモジュレーション系が充実していて、大胆に音を変化させるような積極的な音作りに大いに活用できそうです。
難波さん登場!
さらにデモ演奏として作曲・編曲家で多くのミュージシャンのサポートのほか、自身のバンド「センス・オブ・ワンダー」などでも活動するキーボーディストの難波弘之氏が登場!デモ演奏ではprologueを自在に操りながら、存在感のある音色を多彩に披露しました。
prologueの音の印象について難波氏は「一言では伝えきれないのですが、PolysixとMS-20にFMシンセが加わってハイパーにした感じという印象でしょうか(笑)。それからクロスモジュレーションが付いているのでProphet-5みたいな音も出せますので、色々なことが出来て非常に面白いですね。」と過去の名機になぞらえて紹介。たしかに金属的な響きのある音や強烈なモジュレーションがかかったような音はProphet-5を彷彿させました。
prologueに実際触れてみましたがオシロスコープで波形を確認しながら、ツマミをいじって直感的に音を探す、ハードシンセならではの音作りに時間が経つのを忘れるほどでした。特にオシレーターの部分はアナログとデジタルの魅力が結実した、シンセサイザーの新しい可能性を秘めているように思います。
またデジタル・オシレーターやエフェクト・プログラムをprologueへロードしてユーザーがカスタマイズできる拡張性にも魅力を感じました。誰もが同じ音がするシンセサイザーではなく一人一人違う音を生み出せるシンセサイザーで、ユーザーそれぞれの知識や創造力で積極的に音を作っていってほしいという、KORGからの熱い思いを感じました。
発売は2月24日(土)で、価格はprologue-8が¥162,000、prologue-16が¥216,000、ただいま予約受付中です。
volca mix
volca mixも展示されていました。これは複数のVolcaをライブセットで可能にする4チャンネルミキサーです。コンパクトながらも3台まで一括で電源供給できる機能や、ライブセットでマスターとして活躍する新機能もあります。ステージのvolcaパフォーマンスを実現するためにはとても便利な製品ですね。
発売は2月24日(土)の予定です。
その他
他にもこんな製品がありました。
Arturia
会場の別フロアではKORGが輸入代理店を務めるArturiaの新製品が展示されていました。NAMM 2018で話題になっていたMiniBrute 2、MiniBrute 2S、RackBruteといった製品に、多くの人が注目を集めていました!
作曲・編曲家でキーボーディストの氏家克典氏による解説も行われました。
MiniBrute 2
まずはアナログシンセサイザーのMiniBrute 2です。
何と言っても48 in/outのモジュラーパッチベイが搭載されている事が大きな特徴です。シンセサイザーとシーケンサーの多くの要素をコントロールするための48のCV入出力とユーロラックの組み合わせでさらに多彩な音作りが可能です。外部音声を入力するexit inもありますので、MiniBrute 2に取り込んだ音をSteiner-Parkerフィルターで加工することも可能です。
VCOは2基搭載されていて、下記のような構成になっています。
VCO1:分厚いサウンドを生み出すUltra Saw、三角波の倍音を複雑にするMetalizer内臓。FM機能も搭載
VCO2:サイン波、ノコギリ波、矩形波の選択式。ファイン、コース、LFO操作のための3種類のチューニングモードを搭載
氏家氏の解説動画もご覧ください!
MiniBrute 2S
MiniBrute 2Sは、パッチベイから拡張されたモジュラーシンセをコントロールすることでモジュラーシステムの中心になります。鍵盤の代わりに3トラックのステップシーケンサーとベロシティ対応16のパッドを搭載していて、これらを駆使してフレーズを作ったり様々なパフォーマンスができます。
RackBrute
ユーロラックケースのRackBruteも3Uが展示されていました。MiniBrute 2やMiniBrute 2Sと「LINK COMPATIBLE」機能によって連結できます。こんな感じでセットになるので、ライブやレコーディングなどで持ち運ぶ際にも重宝しそうです。
発売はMiniBrute 2、MiniBrute 2s、RackBruteともに4月下旬の予定です。
V Collection 6
そして発売されたばかりのV Collection 6についても氏家氏の解説がありました。ビンテージシンセ21種類のソフトウェアをパッケージしたこの製品。新たに追加されたBuchla Easel V、DX7 V、CMI V、Clavinet Vと言った4つの音源について、Keylab Essentialで実演しながら熱く解説しています!
- 1′19″〜 DX7 V
- 5′04″〜 Buchla Easel V
- 7′16″〜 Clavinet V
- 7′47″〜 CMI V
今回はシンセサイザー関連の製品が目立ちました。特にprologueは過去の資産や経験を生かしつつ、未来へつなぐための新しい技術が導入されていたのが印象的でした。
次回はまたどんな製品が登場するのか楽しみです。
Writer.Miyazaki
棚卸し休業のお知らせ
【アーカイブ動画公開!】KEMPERを選択する理由はこれだ!クリエイター目線で使いこなす!PROFILING AMPの深層世界!!
2018年2月2日(金)にRock oNで開催されたKemperセミナーのアーカイブ動画を公開します!
Rock oN 渋谷店のPlayers Boothとリファレンスルームを最大限使用した本セミナーはKEMPER PROFILING AMPの魅力とたっぷりと伝える約1時間の内容となりました!
こんな方は是非チェックを!
- ギターアンプのプラグインやアンプシュミレーターの導入を検討しているが何を購入するのがベストなのか分からない
- 「PROFILING」「IR(impulse response)」「モデリング」の違いでどういった音の違いが現れるのかを知りたい!
- 自分の所有するアンプを「PROFILING」しているが良い音にならない… 最適なセッティングやマイク選びを知りたい!
- ギターアンプを所有していないが、良い音を出せる機材を探している。
- ギタートラック込みでの制作を依頼される事が多く、自宅完結であっても聞き手を説得させられる音を探している
セミナー構成
第一部 KEMPER PROFILING AMP を徹底解剖!
宅録でKEMPERを使用する際のI/Oとのセッティングから、他のアンプシュミレーター製品との違い。KEMPERでPROFILINGされた音の特徴と取り扱い方法について、ヘビーユーザーである青木氏の目線でどんどん切り開いて行きます!
第二部 実際にPROFILINGを通して、KEMPERの実力と活用術を伝授!
渋谷店のPlayersBoothを使用し、実際に「PROFILING」の実力を大型モニタースピーカーで体感します。自身が代表を務める「ViViX」でも数多くの「Rig Pack」を発売している青木氏が紐解く「KEMPER」の実力をその耳で是非体感してください。その他のギター素材と聴き比べも…?
当日使用機材
PC
Apple MacBook Pro 15inch 2015mid
Corei7 2.8Ghz Memory 16GB
Audio Interface
Apollo Twin MK2 QUAD ※UADプラグインは使用しておりません。
Guitar Amp Head
Mesa Boogie Triple Rectifire Head 3ch
Guitar Amp Cabinet
Marshall 1960A
PROFILING時 使用マイク
SHURE SM57
Royer Labs R10 (※セッティングはBack)
Monitor Speaker
Focal SM9
セミナー内で使用した比較音源資料
1 リボンマイク使用時の比較試聴コーナー音源素材
2 KEMPERとプラグインアンプシュミレーター比較コーナー音源素材
KEMPER PROFILING AMP シリーズ
大決算大BAZAR FINAL!総勢270overの製品が集う、赤字覚悟の大決算ラストラン!
SPITFIRE AUDIO – ALTERNATIVE SOLO STRINGS新発売!
SampleMagic D2Rにて取り扱い開始!
WES AUDIO _HYPERION 登場!プラグインでリコールする、完全アナログEQ。API500互換モジュール
WES AUDIOの新製品 _HYPERION(ハイペリオン)はプラグインからデジタルリコールが可能なアナログEQ。
WES AUDIOはこれまで_MIMAS(1176系アナログコンプ)や_DIONE(SSL系アナログバスコンプ)といったプラグインコントロールできる製品をリリースしていましたが、そこに念願のEQが加わりました!
プラグインで管理できることで、アナログEQをスタジオのDAWシステムにシームレスにインサートすることができるでしょう。他にはないこの魅力を味わってくださいね!
全てのWES AUDIO製品をeStoreで見る_HYPERION(ハイペリオン)は、完全なアナログ回路で構成された、パラメトリック・イコライザーです。多くの革新的な機能を搭載し、+24dBのヘッドルームを獲得しています。各チャンネルには18個ものVCAを配し、ノイズレスなパラメーター・チェンジと、たいへん音楽的なイコライジングを可能にしています。
_HYPERIONは、WES AUDIOが提唱するAPI500モジュール互換「NG500」の規格で本体のUSBまたは同社_TITAN電源ラック経由でDAWと繋げて使用します。
Feartures:
- +24dBuヘッドルーム
- ステレオ /デュアル・モノ / MSオペレーション・モード
- 4バンドEQ(5dbまたは15dBのブースト/カット・レンジ切替)
- High – 2kHz ~ 25kHz (ピーキング or シェルビング)
- High-Mid – 600Hz ~ 8Khz(w/ Qコントロール)
- Low-Mid -200Hz ~ 2.5Khz(w/ Qコントロール)
- Low -30 Hz ~ 350Hz (ピーキング or シェルビング)
- ハイパス・フィルター(12dB/Oct または 6 dB/Octスロープ)
- 各バンドごとに独立したバイパス・スイッチを用意
- 完全にノイズレスなパラメーター・チェンジ
- アナログ特有のサチュレーションを加えられるTHDモード搭載
- フレキシブルなDAW/Liveプラグインによるトータルリコール
- 12のタッチ・センシティブなエンコーダーを利用した滑らかなオートメーション書き込み
- トゥルー・バイパス
- 入出力メータリングとクリップ監視
- A/B比較試聴のための機能
革新的なハードウェア回路設計
_HYPERIONはフル・アナログのEQデバイスで、+24dBものヘッドルームを確保しています。18個のVCAを各チャンネルに配した革新的なデザインが、ノイズレスで音楽的なイコライジングを可能にしています。
4バンドEQ構成
4バンドのEQ構成に、ブースト/カットのゲインレンジを5dBまたは15dBで切り替えできるフレキシブルな構成。
・High – 2kHz ~ 25kHz (ピーキング or シェルビング)
・High-Mid – 600Hz ~ 8Khz(w/ Qコントロール)
・Low-Mid – 200Hz ~ 2.5Khz(w/ Qコントロール)
・Low – 30 Hz ~ 350Hz (ピーキング or シェルビング)
3つのオペレーション・モード(Stereo/Dual Mono/MS)
 _HYPERIONはステレオ /デュアル・モノ / Mid-Sideの3タイプのモードを搭載しています。様々のアプリケーションにフル対応できます。
_HYPERIONはステレオ /デュアル・モノ / Mid-Sideの3タイプのモードを搭載しています。様々のアプリケーションにフル対応できます。
ハイパス・フィルター
 -12dB/octまたは-6dB/octスロープのハイパス・フィルターを利用可能です。
-12dB/octまたは-6dB/octスロープのハイパス・フィルターを利用可能です。
各バンドごとにバイパス・スイッチを配備
 比較しながらのサウンドメイクがしやすい、各バンドごとに個々にバイパスすることが可能。従来にない使いやすさを実現しています。
比較しながらのサウンドメイクがしやすい、各バンドごとに個々にバイパスすることが可能。従来にない使いやすさを実現しています。
ミックスにカラーリングを行うTHDモード搭載
 THD(Total harmonic distortion)モードにより、シグナルに美しいアナログ・カラーのサチュレーションを与えることができます。
THD(Total harmonic distortion)モードにより、シグナルに美しいアナログ・カラーのサチュレーションを与えることができます。
DAWからのプラグイン・コントロール(デジタル・リコール)
 すべての操作やモードに同期するプラグイン(ステレオまたモノ)により、本体ハードウェアーとプラグイン双方からの操作をリンク。入出力のメータリングやクリップなどの管理はもちろん、セッションごとの設定の「トータルリコール」や「オートメーション」が自由自在に行えます。もちろん音声信号は完全なアナログパスなので、ピュアなアナログ・イコライジングを実行できます。
すべての操作やモードに同期するプラグイン(ステレオまたモノ)により、本体ハードウェアーとプラグイン双方からの操作をリンク。入出力のメータリングやクリップなどの管理はもちろん、セッションごとの設定の「トータルリコール」や「オートメーション」が自由自在に行えます。もちろん音声信号は完全なアナログパスなので、ピュアなアナログ・イコライジングを実行できます。
プラグイン・ソフトウェアはAAX/AAX DSP/VST3/VST2/AUに対応し、無償で入手することができます。
audient iD22価格改訂!
革新的ループ制作ツール Audio Texture 登場!
MACKIE Onyx I/F予約開始!
Rock oNがAvidより、APAC Audio Top Channel Partnerを4年連続受賞!
「APAC Audio Top Channel Partner」4年連続受賞!
2018年2月、Rock oNが『APAC Audio Top Channel Partner 2017』を受賞。Avidより輝くトロフィーと共に表彰されました。
APAC Audio Top Channel Partnerはアジア、オセアニア地区(Asia Pacific)において、Avidオーディオ製品を最も多く販売した実績に授与されました。
弊社はAvidオーディオ製品の売り上げNo.1を国内4年連続で続けており、その業績を評価され受賞になりました。
ROCK ON PROはトータル・システム・プランニングで最適な制作環境を提案します!
ROCK ON PROは、業務用スタジオから個人の制作環境を整えたい方まで、様々なレンジに幅広く対応致します。選任のROCK ON PROスタッフが、豊富な納品実績のノウハウをもとに機材選定から設計/施行、アフターケアに至るまでのご相談を承ります。録音データのストレージネットワークの構築、防音工事、ワイアリング等も是非お任せ下さい。現地視察/施行完了迄を、専任のスタッフと専門業者との連携で責任を持って担当致します。
お見積もり/資料請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください!
http://pro.miroc.co.jp/hd/
Ableton Push2 + Live 9バンドル!
Sonica instruments SHO 新発売!国産メーカーならではの繊細な表現力で笙をDAW上に再現!
日本人が作る日本の伝統楽器音源。SONICA INSTRUMENTSのVirtuoso Japanese Seriesの第四弾 SHO が発売です!
これまで『KOTO 13』『TSUGARU SHAMISEN』『SHAKUHACHI』と非常に難しい奏法を持つ楽器を一流演奏者の息遣いと共に見事にソフト音源化。国内外から非常に高い評価を得ています。
最新作のSHOは雅楽でおなじみのサウンドでありながらしかしその仕組みや奏法があまり知られていない笙(しょう)を見事に音源化しています。雅楽伝統のチューニングやゆらぎは忠実に再現しながらも現代的な西洋音楽にマッチするセッティングやスケールを備えるなど、クリエイターの発想を刺激する格調高い音源といえるでしょう。
笙の音楽的役割や仕組みについて、こちらの動画がわかりやすいです。ぜひご覧ください。
Sonica instruments SHO
Virtuoso Japanese Series第四弾、笙がついにソフトウェア音源化、Kontakt Instrumentsとして登場!
雅楽の三管のひとつ、笙。
17本の竹管をもつその姿から鳳笙(ほうしょう)とも呼ばれ、その音色はまるで天上から降り注ぐ 光。世界初ともいえる本格的な笙のサンプリングを実現、遂にVirtuoso Japanese Seriesに加わりました。

主な特徴
- 笙演奏家・石川高氏による演奏を丁寧にキャプチャーしました。
- 笙の全15本の竹管*の単音と11種類の和音を、個別に全奏法で収録。雅楽から現代音楽まであら ゆる音楽シーンで活用できます。
- 笙の演奏手法を分析し、インストゥルメントモデルを開発。笙特有の和音演奏(合竹)と単音演 奏(一竹)を自由に組み合わせて演奏可能
- 本物の笙と同じ配列の指使いで和音や単音程を指定して演奏可能な2種類のキー・モードを用意。
- 笙の複雑な菅の配置と発音状況を把握
- 雅楽特有のピタゴラス律のほか、平均律や自由な音律を設定可能なスケールチューニングを装備、 古典音楽からコンテンポラリーまでシームレス対応。
- 音が途切れることなく、多彩なアーティキュレーションヘ変化させながら演奏可能なキートリガー コネコション機能
- 無段階かつ自然に音色変化を加えるエクスプレション・コントロール
- 演奏者の人数を3人まで増やせるEnsembleセレクターを搭載、雅楽管絃での合奏に対応可能。
- 24bit、96kHzで録音された生々しく繊細なサウンド(製品は24bit、44.1kHzで収録)
- マルチマイクで収録、Direct、Overhead、Room、Stereo Mixを個別に専用Mixerでミキシングし て音作りが可能
*笙の竹菅は全部で17本ありますが、実際に音が出るのは15本です。
熟練した精密な演奏をレコーディング。
笙の演奏は石川 高(いしかわ こう)氏。雅楽演奏グループにも所属しながらもコンテンポラリー音楽にも精通した石川氏の精密な演奏を通して、複雑な笙の楽器構造を分解し、竹菅1本1本を丁寧に録音しました。
演奏者
石川 高
いしかわ こう
笙(しょう)
1990年より笙の演奏活動をはじめ、国内、世界 中の音楽祭に出演してきた。 雅楽団体「伶楽舎(れいがくしゃ)」に所属し、 雅楽古典曲や現代作品を数多く演奏している。
笙の独奏者としても、様々な音楽家、作曲家と共 に活動し、また即興演奏を行う。催馬楽など雅楽 の歌唱でも高い評価を受けている。 和光大学、学習院大学、沖縄県立芸術大学、九州 大学にて講義を行い、朝日カルチャーセンター新 宿にて「古代歌謡」講座を担当している。
2016年には、Festival fur Aktuelle Klangkunst (Trier)、No Idea Festival (Austin)、The Empty Gallery (Hong Kong)、Sounds to Summon the Japanese Gods (Japan Society, New York)、 2017年には、In a Winter garden (Stanford University, California)、Yugenism: Animated Soundscapes of the Japanese Sublime (London)、ISCM World New Music Days 2017 (Vancouver) 等に参加した。
公式ホームページ:http://radiant-osc.com/
笙特有の演奏表現をリアルに再現する、専用発音メカニズムとインターフェースを開発。
合竹(あいたけ)と一竹(いっちく)での演奏を実現
複数の菅を同時に鳴らす11種類の和音(合竹) “Chord Tone”と1本の菅を鳴らす単音(一 竹) “Single Tone”が独立して演奏可能。もちろんアーティキュレーション・コントロールも 独立して行うことが可能です。
Chord Tone(合竹):C2~F3(白鍵のみにアサイン)
Single Tone(一竹):G3~C6
パイプ・インジケーター
複雑な竹菅の配列と発音状態をモニター可能なパイプ・インジケーターを装備。 菅の音名が古典音名でわかりやすく表示され、Chord Tone(合竹)演奏時には11種の和音名も表 示されます。また、後述のスケールチューニング・ボックスと連動して動作するため、各竹菅 の音を鍵盤の音程でモニタリングでき、とても便利です。
古典の演奏を忠実に再現するキー・モード
クロマチック・キー配列のほか、笙と同じ指使いで演奏可能なフィンガリング・キー配列を用意しま した。このキー・モードでは白鍵を竹菅に見立てています。両手の指を白鍵に置き、まるで15本の竹菅の穴を塞ぐように演奏することができます。
笙の演奏家の方に非常に使いやすいばかりでなく、楽器の理解・学習にも大いに役立ちます。
Chromatic
一般的なクロマチックスケールで発音。シングルトーン15音以外の音程も演奏できるためどんな音 楽にも対応可能です。
Trad. Fingering
白鍵のみにシングルトーン15音を配列。C4より低音側には左手で押さえる菅を順番に配列、D4よ り高音側には右手で押さえる竹菅の音を配列。
スケールチューニング機能

笙の演奏可能音域について、全クロマチックピッチを個別にチューニングできます。
雅楽で使われるピタゴラス音律や、平均律に簡単に設定できるほか、カスタム・チューニングを作成して演奏することができます。
設定した値はもちろん保存して使うことが可能です。
12_scale-tuning
Chord Tone(合竹)
430Hzと440Hzの基本ピッチに設定可能。
Single Tone(一竹)
430Hzピタゴラス音律、
440Hzピタゴラス音律、
440Hz平均律にセットすることができ、
それをベースに1鍵ごとに
ファインチューニングが可能です。
演奏が途切れることなく奏法の変化が可能なキートリガーコネクション
延々と続く持続音が特徴の笙ですが、息遣いによって多彩なアーティキュレーションを表現可 能です。そしてそのほとんどが音が持続させながら自然に繋がって変化していきます。このよ うな挙動を再現するキートリガーコネクションを装備、演奏中にキースイッチを入れることで 任意のアーティキュレーションへと自然に変化させることが可能です。
無段階に音色の強弱を表現するエクスプレッション
息の強さで吹き音を自在にコントロール可能。
サンプルベースでありながらも、滑らかでダイナミックな息づかいを表現することができる ため、さながらウィンドコントローラーのような感覚で鍵盤演奏が可能です。
音の立ち上がりをコントロールするブロウスピード
エクスプレッションに加え、息のスピードによる音の立ち上がりスピードに汎用コントロー ラーでコントロールでき、もたつきのない演奏が可能になります。
ポリフォニックレガート奏法
演奏中に音を積み重ねたり、ある音だけを違う音程に移動させるなど、単音でも和音でも 可能なポリフォニックレガート奏法が可能です。複数の竹菅を持つ笙ならではの奏法とい えるでしょう。ポリフォニックレガートはSustain Pedalで瞬時にON/OFFが可能です。
笙特有のアーティキュレーションを豊富に収録
ストレート(吹き音/吸い音)、フラッター(吹き音/吸い音)、スフォルツァンド、クレッ シェンド、トレモロスロー(吹き音/吸い音)、トレモロファースト(吹き音/吸い音)な ど、あらゆるアーティキュレーションをChord Tone(合竹)とSingle Tone(一竹)で収録し ています。
3人まで増やせる、アンサンブル機能
雅楽の管絃では楽器ごとに複数の奏者が配置され、厚みのあるユニゾン演奏を行います。 ソロ、2人、3人のモードを選択でき、各奏者の演奏のずれ具合、配置の広がりをコントロール可能です。
収録アーティキュレーション
Chord Tone(合竹)
ストレート(吹き音/吸い音)、フラッター(吹き音/吸い音)、スフォルツァンド、クレッ シェンド、トレモロスロー(吹き音/吸い音)、トレモロファースト(吹き音/吸い音)
Single Tone(一竹)
ストレート(吹き音/吸い音)、フラッター(吹き音/吸い音)、スフォルツァンド、スライ ドアップ
※Chord Tone、Single Toneは同時に発音、独立したキースイッチでアーティキュレーション を選択可能。
※すべてのアーティキュレーションがキートリガーコネクションで接続可能。
Audio Mixer
Direct、Overhead、Room3種類のステレオマイクポジション+Stereo Mixで収録。
チャンネル毎に用意されたVolume / Stereo Width / Pan / Reverb Send / EQ で自在にミキシング 可能です。さらに高品質コボリューション・リバーヴを搭載、Instrument上でクオリティの高い 音作りが可能です。また各マイクチャンネル毎にDAWトラックへのパラアウトが可能なマルチア ウトプット・バスを用意、緻密なミキシング・セッションにも対応可能です。
大決算大BAZAR USED &展示機 PICK UP!
大決算大BAZAR は2月28日まで。最後のカウントダウンに入っています。そこで一期一会のUSED & 展示機 をPICK UPします!Rock oNの目利きでコンディションをチェックして値付けした貴重なUSEDと、Rock oN店頭で実働していた間違いないクオリティの展示機。どれも1点限りの大特価でご奉仕いたします!
AURORA AUDIO / Stinger 店頭展示機 ¥198,000
デスクトップにあるOld Neveサウンド。マイクプリ&EQ&D.I
Aurora AudioはNEVE正当継承ブランドの一つとされ、今もエンジニアの羨望を集める1073マイクプリアンプの設計を受け継いだ同社製品GTQ2が高い人気を誇っています。
この「Stinger」は多くのクリエイターに向けて作られたデスクトップタイプ1chマイクプリアンプで、コストを抑えながら扱いやすいデスクトップタイプへと変貌を遂げています。また、新たな機能として独立したInstruments Inputを搭載し、独自のイコライズドオーバードライブによってより幅広いサウンドを得ることを可能にしています。
 本製品のブロックダイアグラムを見てみると興味深いことにマイクプリアンプ+Gt.InputとInstrument Inputが完全に独立していることが挙げられます。よって、ボーカルとギターを同時に収録することや、ベースギターをインプットした後に更にInstrument Inputへ入力することでイコライザとオーバードライブ回路を同時に仕様することが可能です。
本製品のブロックダイアグラムを見てみると興味深いことにマイクプリアンプ+Gt.InputとInstrument Inputが完全に独立していることが挙げられます。よって、ボーカルとギターを同時に収録することや、ベースギターをインプットした後に更にInstrument Inputへ入力することでイコライザとオーバードライブ回路を同時に仕様することが可能です。
また、両回路とも+4dBのライン入力が可能で、オーディオインターフェースからの出力をそのまま入力しサウンドへの色付けやイコライジング・オーバードライブをかけることもできます。
尚、Gt.Input及びInstrument Inputはそれぞれ1Mohm、10Mohmのインピーダンスとなっており、共にベースギター等の楽器入力として仕様することができます。
DynaMount / X1-R 未開封品 ¥69,800
マイキングをリモコン制御。リコールも可能なマイキングポジショナー
優れたミックスは優れたマイキングが必要。DynaMountのマイクポジショナーは、まるであなたのアシスタントのようにマイキングを遠隔操作で行いポジショニングをバッチリ決めることができます。
コントロールはiOS、Android、Chrome appsのAppで。WiFiもしくUSB経由で接続します。指先一つでマイクを移動させることができ、もちろんリコールも可能。
製品はX-Yの2軸モデルの『X1-R』、コンパクトな1軸モデルの『V1-R』の2種類のラインナップで、あなたのニーズに応えます!
Fractal Audio Systems / FX8 店頭展示機 ¥119,800
ギタリスト垂涎のAXE FXのエフェクターをフロアペダルに集約!
真空管アンプを知り尽くしたFractal Audio Systems社だからこそ成し得たアンプ・インターフェース・フォーマット。こだわりのリアルアンプ・サウンドはそのままに、無限のエフェクトで彩ります。
PCによるプリセットの編集、ファームウェア・アップデートは、FX8の可能性を無限大に拡げます。
What is FX8 ?
- アンプ+キャビネットシミュレーターを無くすことによりCPUの処理能力を極限までアップ。接続したリアルアンプのサウンドを変化させずにフレキシブルなシグナル・ルーティーンを実現しました。
- プリセット毎に異なるエフェクトボードシステムを製作する感覚で22タイプ 33ブロックのエフェクターから8個が選択できます。
- 各エフェクターはパラレル/シリーズ接続を自由に設定できるだけでなく、ギターアンプ入力の前段に接続するか、エフェクトループに接続するかの選択も行えます。
- 8個のフットスイッチはエフェクターだけではなく、RELAYブロック、MIDIブロックにもアサインが可能。アンプのチャンネル切替だけでなく、MIDI対応機器のコントロールもリアルタイムで行えます。
- 8個のエフェクトペダルをダイレクトにオン/オフする感覚の “STOMP BOX”モード
エフェクトボードシステム全体を瞬時に切替える感覚の”PRESET”モード
エフェクトボードシステムでエフェクターのオン/オフ状態をプリセットする感覚の”SCENE”モード
プレーヤーのデマンドに合わせた操作方法のギターサウンドシステムが構築できます。

日東紡音響エンジニアリング / AGS SYLVAN 店頭展示機 ¥89,800
スタジオ施行のノウハウが生んだ音響拡散技術があなたの部屋の問題を解決!
日本を代表する音響施工会社である日東紡音響エンジニアリング。その豊富な経験とノウハウから生まれたのが柱状拡散体のAGSです。
AGSは、わずか60cmの奥行で、低音の抜けの良さと、癖のないナチュラルな響きをもたらすルームチューニング機構です。
森の中で感じる果てしない空間のひろがり。無数の木々が懐深く連なる森の中は,低域の抜けの良さと中高域の緻密な響きが得られる理想の音場といわれています。こうした森の音響効果に着目し,国内外のスタジオ造りにおける豊富な実績と長年培ってきた音響シミュレーション技術を駆使し開発されたのが、「Acoustic Grove System (AGS)」です。
SYLVANシリーズの本製品は、AGSがもたらす斬新な音空間を手軽に実現したいというご要望にお応えするため、AGSのコア技術をコンパクトにまとめました。コンパクトな形状の中に円柱群を独自の音響技術に基づいて配置しています。置き場所を選ばず,部屋のデザインやレイアウトにマッチした配置が可能です。標準でアジャスタが付属しており垂直調整が可能ですが,キャスター(オプション)に交換し簡単に移動することもできます。
SYLVANはレコーディングスタジオ、放送局といったプロの音創りの現場から,オーディオルーム、ホームシアター、楽器練習室まで,様々な用途の部屋でお使いいただいております。部屋の壁面全面に配置しなくても,わずか1、2本を室内にするだけでも別の部屋にいるかのように音場感が大きく向上します。
AMEK / 9098DMA ¥148,000
ルパートニーブ氏設計の人気の高いマイクプリ9098DMA。この魅力は何と言っても存在感あるサウンドでしょう。一言で表すのはなかなか難しいのですが、音圧感が有りながらもスムースな独特の質感を持っています。いわゆるオールドニーブ系と比べるとよりクリーンな印象ですね。さらに本機の魅力は他のオケと混ぜ合わせた時に真価を発揮します。存在感は有りながらも、全体と自然になじむのです。
現在入手困難な機材の一つでもあるのでこの機会にぜひ検討ください!
SSL / Alpha Channel ¥99,800
「SSLのサウンドをエンジニアに頼ること無く、もっと多くの人に届けよう。しかし、それはSSLの財産を生かした物でなくてはならない」という理念から生まれたAlpha Channel。
Dualityにも採用されているVHD回路を搭載し、2次倍音(真空管に代表される厚みのある倍音)と3次倍音(トランジスタに代表される倍音。音が前に立ってきます)を効果的にコントロールでき、ピュアなマイクプリに対し効果的に倍音を加えることによってあらゆるソースを柔軟に音楽的にアプローチすることができます。
私は何年か前にこのAlpha Channelをあるサンバチームのレコーディングで積極的に採用しました。そこではオーバーダビングも絡む非常に多くの楽器をレコーディングしました(その際、4chマイクプリであるVHD PREもあわせて使用しました)。非常に多くのトラック数をダビングすることを想定していたため、なるべくS/Nを高く保持する意味でも採用の決め手となりました。
ほぼすべてが打楽器で構成されるまさに倍音地獄のレコーディングなわけで、安易に録ってしまうとのちのち収集つかなくなる危険性がプンプンするセッションでしたが、このVHDツマミを積極的に採用することにより、
質感を整え、思った通りのキャラクター、押し出し感を録りの段階で得ることが出来、その後のMixが非常に簡素で楽になった経験があります。低ノイズで多くの楽器をダビングしてもノイズが気になることは有りませんでした。
そのときは、Analog in/outの接続としてPro Toolsに取り込みましたが、このAlpha ChannelはライトリミッターをもったADコンバータが搭載されているのでDAWにロス無く信号を送ることも可能です!EQも各楽器にトリートメントの意味で積極的に採用し(このEQもVHDとの絡みで面白い相乗効果を生んでくれるんですよ)、結果的に非常にスムーズにMIXができクリアな音場を保持出来ました。
Antelope / Zen Studio ¥138,000
「信頼のAD/DA変換」と「オーディオインタフェース」の融合
オーディオプロダクションの多様性に応える入出力と極めて強力なDSPプロセッサーを搭載し、バンドマンやクリエイターからエンジニアまで、全ての音楽制作者の要求に応えるオーディオI/Fが Zen Studio。
Zen Studioは非常に多くの入出力を持っています。特筆すべきは12chものマイクプリアンプ。通常ドラムをマルチマイクで最低限それぞれに独立してマイキングをしようとすると1タムの場合
【Kick】【Snare Top】【Snare Bottom】【HiHat】【Floor tom】【Hi tom】【Top x2】
といった構成が一般的ですが、それだけでも8chのマイクプリが必要です。8chものマイクプリを搭載されたオーディオインターフェイスは他社メーカーを含めても限られた製品しかなく、その中で性能と信頼性を考えると非常に高額となってしまいます。また8chものマイクプリをアウトボードを揃えようとすると更に高額となり、携帯性に劣ってしまうことも。
Zenは余裕を持たせた12chものクラスAマイクプリを搭載しているので、上記の構成のマイキングにさらにRoomマイクを加えたり、Bassのラインやギターを同時録音したりと、バンド録音やライブ収録などでコンパクトなボディながら堅牢なコアシステムになること間違い無しです。
それだけにとどまらず、追加に8ラインin/outや16ch ADATコネクター、SPDIF I/O ワードクロックI/O etcと豊富な入出力を装備します。
音質は明るいキャラクターながらもAntelopeらしい中低域の粘りと押し出し感が感じられました。バンド系はもちろんクラブ系、Jazzなど幅広いジャンル、シーンで活躍してくれることは間違いありません!ライブ録音、スタジオレコーディングの用途の他、自宅でもメインオーディオインターフェイスとしてプロフェッショナルな要求にも応えられるでしょう。
Blue Microphones / Bottle ¥328,000
R&BやPOP/ROCKの定番。きらびやかに音抜けするフラッグシップマイク!
Bottleは、ヴィンテージ・マイクの深い味わいとモダン・テクノロジーを融合した、20世紀を代表するアイコニックなレコーディング・マイクの一つです。
専用パワーサプライのPower Streamは、偏極電圧を9段階で切り替えられるセンシティビティー・ノブを装備しており、クリーンで安定したパワーをマイクに供給します。
スタンダードな「B-6」カプセル(カーディオイド、モダンサウンド)に加え「B-0」カプセル(カーディオイド、ブライト&シルキー)も付属し、ボーカル録音用に最適です。
収録カプセル
B0
単一指向性のラージ・ダイヤフラム。ブライトでありつつシルキーなサウンドでヴォーカルやギター、パーカッションなどトップエンドの伸びが欲しいときに最適です。

B6
単一指向性のラージ・ダイヤフラム。デュアル・バックプレート付き。Bottleに標準搭載されるカプセルです。モダンでプレゼンスの効いた高域と決して膨らみすぎない存在感のある低域を持ちます。リード/バックグラウンド・ヴォーカル、ピアノ、ギター等幅広く使用できます。

『田辺恵二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞVIDEOS Vol.37』公開!

作曲からミックスまで、田辺さんのノウハウを垣間見ながら、その中で制作風景や気になるクリエーターを紹介したり、最新の機材をいじっちゃうというこの企画。
第37回目はArturiaより発売中の、「音楽制作に寄り添った次世代のオーディオインターフェイス:AUDIO FUSE」と「ここ100年間の音楽史を築き上げた伝説的キーボードのすべてが揃うコレクション:V Collection 6」を製品レビュー!
ご意見/ご感想をお待ちしています。
このムービーの感想をぜひ田辺恵二さんに伝えてください。あなたのご意見を本人まで届けます!
過去のアーカイブはこちらから